- 著者: 一柳 慧(いちやなぎ とし)
- 出版社: 平凡社
- 価格: 2200円
- 発売日: 2016年08月05日
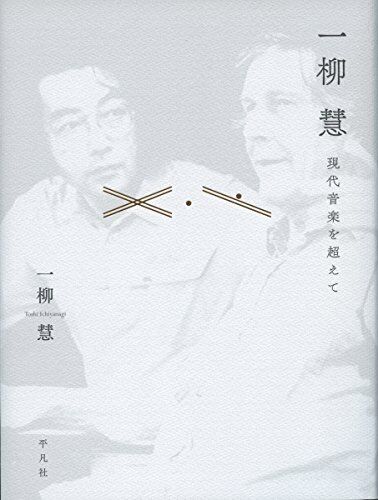 一柳慧(いちやなぎとし)。1933年、神戸生まれ。2022年10月7日没。父 信二(1902年生まれ)チェロ奏者。パリに4年留学経験あり。母 光子(1903年生まれ)ピアニスト。アメリカのオハイオ州の大学で2年留学。1949年 16歳で毎日音楽コンクール(今の日本音楽コンクール)作曲部門1位を獲得後、母の留学中のつてを頼ってアメリカへの留学を決める。1952年 2週間の船旅でオークランド〈サンフランシスコ近くの港)到着。ミネソタ大学音楽学部での勉強を始めたのち、ニューヨークのジュリアード音楽院への奨学金を得て転居。これだけでも、「すごいな」と思います。留学先をアメリカとしたのは、世界大戦で疲弊した欧州よりも可能性に満ちている、と父が判断したからで、その判断は正しかったとのこと。そして、ジョン・ケージと知り合い、その弟子と見做されるように。ジョン・ケージといえば、全く音を出さずに演奏者がステージ上に存在するという「4分33秒」(1952年)が有名ですが、この曲、日本の鈴木大拙の教えを端的に音楽の世界で実現したものとのこと。ジョン・ケージのコンセプトは「論理に縛られず、開かれた耳で音楽を書く」p.22ことで、自然との共生を説く東洋思想の影響を受け、「人間中心主義」に根ざしたヨーロッパ音楽に異議を唱え、自然や生活の中にあるさまざまな音に耳を傾け、無心に曲を作ったのだそうです。一柳慧自身、シェーンベルクの12音技法やセリーの音楽院技法などに懸命に取り組み、そこで行き詰まっていたところ、「ケージの思想や発想がそこから解放してくれた」と回想しています。なるほど。今の若手音楽家たちが、再びケージの音楽に光りを当てているように思いますが、こういう音楽史の流れを知ると、納得です。そして、一柳慧氏の言葉として印象に残ったのが「既成の概念を破壊し、新しい音楽を目指すようになる私の方向性は、戦時中の体験への反動として生まれたとも言えそうです。」(p.47)とのくだり。そして、前衛音楽へと突き進むわけですが、作曲しても、曲というものは演奏者に演奏してもらえないと、この存在価値がない。しかし、前衛音楽は実力のある演奏者による演奏を滅多に望めず、前衛に関心のあるごく一部の人、または作曲科同士で演奏することになり、一部にしか共和されない「閉ざされた音楽」になってしまうわけです。「作曲と楽器演奏の技術が互いに相乗効果を生み出しながら進歩しえきた歴史は無視できない」「もう少し伝統的なやり方で新しい音楽を作ることはできないか」(p.61)そうして「前衛の終わり」にたどりついた答えが「人間の生理に寄り添う音楽」だったのだそうです。以前、TV番組〈確か「題名のない音楽会」)で、ステージ上の卓球台でピンポン玉を打ち合う音が、不思議な音色に変換して、増幅される「オープン・ダイアローグ」というパフォーマンスを視聴したことがあり、とても面白く感じました。これも、人間が行為すくことに意味があったのですね。「間」を大事にする邦楽、雅楽の哲学を取り入れる直線的に進むのでなく、東洋的に循環器する時間軸を考えるなど、芸術は哲学なのだなあと納得しました。読みやすい音楽哲学書、とも言えると思います。
一柳慧(いちやなぎとし)。1933年、神戸生まれ。2022年10月7日没。父 信二(1902年生まれ)チェロ奏者。パリに4年留学経験あり。母 光子(1903年生まれ)ピアニスト。アメリカのオハイオ州の大学で2年留学。1949年 16歳で毎日音楽コンクール(今の日本音楽コンクール)作曲部門1位を獲得後、母の留学中のつてを頼ってアメリカへの留学を決める。1952年 2週間の船旅でオークランド〈サンフランシスコ近くの港)到着。ミネソタ大学音楽学部での勉強を始めたのち、ニューヨークのジュリアード音楽院への奨学金を得て転居。これだけでも、「すごいな」と思います。留学先をアメリカとしたのは、世界大戦で疲弊した欧州よりも可能性に満ちている、と父が判断したからで、その判断は正しかったとのこと。そして、ジョン・ケージと知り合い、その弟子と見做されるように。ジョン・ケージといえば、全く音を出さずに演奏者がステージ上に存在するという「4分33秒」(1952年)が有名ですが、この曲、日本の鈴木大拙の教えを端的に音楽の世界で実現したものとのこと。ジョン・ケージのコンセプトは「論理に縛られず、開かれた耳で音楽を書く」p.22ことで、自然との共生を説く東洋思想の影響を受け、「人間中心主義」に根ざしたヨーロッパ音楽に異議を唱え、自然や生活の中にあるさまざまな音に耳を傾け、無心に曲を作ったのだそうです。一柳慧自身、シェーンベルクの12音技法やセリーの音楽院技法などに懸命に取り組み、そこで行き詰まっていたところ、「ケージの思想や発想がそこから解放してくれた」と回想しています。なるほど。今の若手音楽家たちが、再びケージの音楽に光りを当てているように思いますが、こういう音楽史の流れを知ると、納得です。そして、一柳慧氏の言葉として印象に残ったのが「既成の概念を破壊し、新しい音楽を目指すようになる私の方向性は、戦時中の体験への反動として生まれたとも言えそうです。」(p.47)とのくだり。そして、前衛音楽へと突き進むわけですが、作曲しても、曲というものは演奏者に演奏してもらえないと、この存在価値がない。しかし、前衛音楽は実力のある演奏者による演奏を滅多に望めず、前衛に関心のあるごく一部の人、または作曲科同士で演奏することになり、一部にしか共和されない「閉ざされた音楽」になってしまうわけです。「作曲と楽器演奏の技術が互いに相乗効果を生み出しながら進歩しえきた歴史は無視できない」「もう少し伝統的なやり方で新しい音楽を作ることはできないか」(p.61)そうして「前衛の終わり」にたどりついた答えが「人間の生理に寄り添う音楽」だったのだそうです。以前、TV番組〈確か「題名のない音楽会」)で、ステージ上の卓球台でピンポン玉を打ち合う音が、不思議な音色に変換して、増幅される「オープン・ダイアローグ」というパフォーマンスを視聴したことがあり、とても面白く感じました。これも、人間が行為すくことに意味があったのですね。「間」を大事にする邦楽、雅楽の哲学を取り入れる直線的に進むのでなく、東洋的に循環器する時間軸を考えるなど、芸術は哲学なのだなあと納得しました。読みやすい音楽哲学書、とも言えると思います。
カテゴリ:【書籍レビュー】 > 音楽関係の本
『MAROの“偏愛"名曲案内 ~フォースと共に』
- 著者: 篠崎史紀
- 出版社: 音楽之友社
- 価格: 1650円
- 発売日: 2022年01月26日
NHK交響楽団のコンサートマスターにして、自ら「マロオケ」も率いる篠崎史紀(通称マロ)氏。その人柄が伝わる一冊。
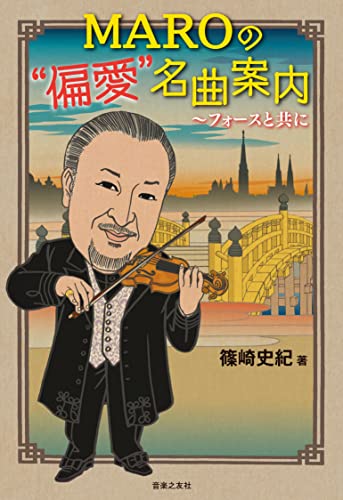
本書は、音楽事典でも楽曲解説書でもなく、作品に対する私の秘めたる愛(完全なる偏愛です!)を書き綴った本です。(「プロローグ」より)とありますが、その「偏愛」ぶりに至る体験、氏の感じる物語などが書かれている部分が印象に残りました。
最初のカテゴリーは「◆ヴァイオリン曲」。
冒頭に取り上げられたのは、バッハの「シャコンヌ」です。
氏が小学生のとき初めて挑戦した際は「重音の多さと楽譜の情報量の少なさに挫折」。
「中学生」のときに「この曲のテーマはメロディの部分ではなくオスティナート・バスだ」と気がつき、各声部を色分けして「塗り絵ノート状態」にしたのだとか。
この楽譜で「自分なりの多角的視点によるアナリーゼを考えることができ」、
この経験が「のちに自分にとって大事な宝物になった」のだそうです。共感!
このカテゴリーでは「デュオというアンサンブルを通して真摯に音楽と作曲家に向き合うこと」の重要性を強調し、
協奏曲や、ソロパートのテクニック性にばかり目を向けないように、と力説されています。
クライスラーの「愛の悲しみ」では(1~31小節)が「ヨーロッパ特有の薄暗い屋根裏部屋」で恋煩いに苦しむ男性、その後、弱気になるも、フェルマータの「ミ」の音で妄想の世界に……といった具合に、細かくマロ物語を解説。
うんうん、と納得しながら読めます。同様に「愛の喜び」もあり。
カテゴリーは
「◆管弦楽曲」「◆交響曲」「◆協奏曲/声楽曲」「◆室内楽曲」と続きます。
協奏曲として取り上げられたのは、ヴィヴァルディの「四季」とチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲」の2曲だけ。ちょっとびっくり。
チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲」は、アメリカのビルボードで第1位を獲得した唯一のクラシック曲とのこと。
その特徴として、氏がとり上げるのが、各楽章の冒頭です。
・第1楽章冒頭:ホルンで始まる序奏。冒頭からオケとピアノが同時にメロディーを奏でる
・第2楽章冒頭:静かな湖畔の水面に朝露が落ちて波紋が広がるようなピッツィカートのみ
・第3楽章冒頭:いきなりティンパニの一打で始まるインパクト
なるほど、と思いました。
体験談と共に語られるので、すんなりと入ってきます。
マロ氏が人気を博されているのは、このあたりのセンスの良さもあるのだろうなと思いました。
タイトルの「フォース」は映画「スター・ウォーズ」のアレです。
ご両親の教育方針とともに、子ども時代から「ハマったもの」の遍歴を語るコラム、
その総まとめともいえる最後の「MARO”裏”プロフィール」も、なかなか面白かったです。
『もし大作曲家と友だちになれたら…―音楽タイムトラベル』
著者: スティーブンイッサーリス、板倉克子
出版社: 音楽之友社
価格: 2750円
発売日: 2003年02月01日
著者は世界的に活躍するチェリスト。
原題『なんでベートーヴェンはシチューをほっぽったか』。
6人の作曲家をテーマに、子供のために書いた本の日本語訳です。ユーモアたっぷり。

著者は世界的に活躍するチェリスト。
原題『なんでベートーヴェンはシチューをほっぽったか』。
6人の作曲家をテーマに、子供のために書いた本の日本語訳です。ユーモアたっぷり。

本の見返しの文言が本書をよくあらわしてます。
子どもから大人まで楽しめるクラシック音楽入門書
- バッハ、モーツァルト、ベートーベン、シューマン、ブラームス、ストラビンスキーの6人の作曲家について
- どんな人だったのか?
- どんな今日をつくったのか?どの作品をきくとよいか?
- 人生で、どんな楽しいこと、どんな悲しいことがあったか?
ユーモアをまじえて、わかりやすく紹介します。
著者のイッサ―リスは、先月(2022年9月)、来日してコンサートに出演していました。
また、先日読んだ『ラドゥ・ルプーは語らない。──沈黙のピアニストをたどる20の素描(デッサン)』にも、ルプーの思い出を寄稿していました。
そんなことがきっかけで手に取った本です。
既に知っていることも多々ありましたが、何と言っても、イッサ―リス氏の「シューマン愛」がひたひたと迫ってきて、印象に残りました。
次のフレーズで、納得することでしょう。
ごくおおざっぱにいうなら、バッハの音楽には神の目からみた世界が示されている。モーツァルトの音楽は大自然の一部のようなものであり、ベートーベンは全人類に向けて語る。では、シューマンはどうだろう?シューマンの音楽は、ローベルト・シューマン個人の感じ方や気持ちを伝えてくれるが、それでいて、ぼくたちみんなに語りかけてくれる。かれの感情はあまりにも強く、あまりにも真に迫ってくるので、ぼくたちはかれの中に自分自身を見つけ出すのだ。かれが人生で経験したことは全部、音楽の中にどっと注ぎ込まれているため、かれほどじかに知り合いになれたような気にさせてくれる音楽家は、ほかにはいない。(p.139)
続く二人の音楽家は、
「ハリネズミのブラームス」
「自己中心的なストラビンスキー」
とまとめられるかもしれません。
あっという間に楽しく読める本でした。
『楽器の科学 ーー美しい音色を生み出す「構造」と「しくみ」』
著者: フランソワ・デュボワ、木村彩
出版社: 講談社
価格: 1100円
発売日: 2022年04月14日
科学の知見としての「音」と、音楽の世界での「音」をつなげて解説する書。著者は日本在住のフランス人マリンバ奏者。音楽ホールについても忌憚のない意見が述べられています。

構成は
・第1楽章 作曲の「かけ算」を支える楽器たち――楽器には5種類ある
・第2楽章 楽器の個性は「倍音」で決まる――楽器が奏でる「音」の科学①
・第3楽章 楽器の音色は「共鳴」が美しくする――楽器が奏でる「音」の科学②
・第4楽章 「楽器の最高性能」を引き出す空間とは?――コンサートホールの音響科学
・第5楽章 演奏の極意――世界的ソリスト10人が教えるプロの楽器論
音の高さは、ヘルツ(Hz)という単位であらわされる振動数で決定しますが、音楽で基準音となっている「ラ」の高さは、今は国際基準では440Hzに調整されています。
とはいえ、この「ラの音の高さ」、実は、歴史的にも、地域的にも、同一ではないそうです。
例えば、
・バロック音楽では415Hz、
・ヘンデル(1965-1759)は423Hz、
・モーツァルト(1756-1791)は422Hz。
そもそも、楽器は温度や湿度によって音程が変化する(温度が低いと、音程も下がる)ため、演奏家たちは演奏環境によって異なる音程の基準音で演奏するのが普通だったのだとか。
現代でも、オーケストラによって差があり、
・MET(メトロポリタン歌劇場)管弦楽団、ロンドン交響楽団は440Hz、
・ベルリン・フィルハーモニー交響楽団は445Hz(カラヤン時代は446Hz)、
・NHK交響楽団、フランス国立管弦楽団、ニューヨークフィルは442Hz、
といった具合。
オーケストラの伝統、オーケストラが本拠地とするホール常設のパイプオルガンの基準音などなど、いろいろな縛りにより、こうなるのだそうです。
ほう、ほう。
カーネギーホールが、改装の結果、音響が劣悪になって大騒動を引き起こした等のエピソードも面白く読みました。
訪れたホールの空間に木材がふんだんに使われていたなら、それは音響技術者による設計というより、むしろデザイナーによる意匠だったり、発注したクライアントの要望であることのようが圧倒的に多いでしょう。
もしかすると、美しく成熟したバイオリンのような高級な木材を惜しげもなく使うことで、コンサートホールでも艶のある音響が生まれる……というイメージがあるかもしれませんが、残念ながらそうではないのです。(pp.173-174)
こんな指摘にも、びっくりさせられました。
「音響の素晴らしい木のホール」という謳い文句、度々目にする気がします。
ただ、ホールで音楽を聴くという体験は、そのホールにたどりつくまで、客席に着いてからの心理状態も大きく影響するもので、ただ、音響だけに配慮すればいいわけではない!という指摘にも、なるほど共感。
最終章「演奏の極意――世界的ソリスト10人が教えるプロの楽器論」では、次の質問(要約)の答えが掲載されています。
Q1:あなたにとっての「良い楽器」とは?
Q2:あなたと楽器とのパートナーシップ(楽器が演奏の音楽性を引き上げた等)の話
Q3:最高の、また、最低の音楽ホールの音響体験
この結果を載せるのは著作権上問題になりそうな気もするので、控えます~。
なかなか面白く読めました。
『老後とピアノ』
朝日新聞の編集委員を退職後、ピアノにドはまりしたアフロヘアの稲垣さんによる、ぶっちゃけピアノライフ満喫話。今や、ピアノ愛好家の間で超絶話題になっている本です。

著者: 稲垣えみ子
出版社: ポプラ社
価格: 1650円
発売日: 2022年01月19日

大人のピアノ、つまり中高年になってからやおらピアノを弾くって、その「思うようにならなさ」といったら、あーた!指は動かないわ頭は動かないわ楽譜は老眼で見えないわ、加えて大人には「見栄」ちゅう余計なもんがありまして、ちょっとでも人に聴かれてるとなったら子供の頃はありえなかったド緊張はするわで、百難去ってまた百難。(p.5)
こんなノリで、非常に楽しい語り口です。あっという間に読了。
構成は次のとおり。
Chapter1 40年ぶりのピアノ
Chapter2 弾きたい曲を弾いてみる
Chapter3 動かぬ体、働かぬ脳
Chapter4 ああ発表会
Chapter5 老後とピアノ
ピアノを持たず、行きつけのカフェ常設のピアノを借りて練習に励み、その記録を雑誌『ショパン』に連載した著者。そもそもは『ショパン』の編集長もそのカフェの常連で……ということで、とんとん拍子に話が進んだ、とのこと。
いやあ、ビジネス界で立派に出世を遂げて方だけのことはあって、
ピアニストである先生の指導を受けつつ、見事に練習に励まれ、めきめきと上達を遂げていくのでありました。
40年ぶりのモーツァルト「きらきら星変奏曲」に始まって、
ショパンのワルツ 嬰ハ短調、
ベートーヴェンの悲愴 第2楽章、
ドビュッシーの「月の光」
、
お見事な邁進ぶりです。
そして、見事なスピードで、あれこれ得心されていくのです。
・「手が痛くない」ことが正解だと気づき、ストンと力が抜け、ゆっくりゆっくり練習を大切にする。
・リラックスして、間違えてもいいやという気持ちで練習を続ければ、いつかは指が覚えてくれると気づき、頭も体もすっと軽くなる。
・楽譜の指示どおりに弾くことの大切さに気付き、楽譜を真剣に読み込むようになる。
・ステージ発表に臨めば、「聴いてもらっている」という感謝の気持ちが湧き上がり、平常心で、精いっぱいの演奏ができた。
感服でございます。
これを、たったの数年で会得しちゃったって、信じられません。
私、年数だけは、馬鹿みたいに長いこと、ピアノにさわってはいますけれど、
上に挙げたもののうち、会得できたことなんて、ほんのわずかですもの。
そして、巻末の附録「わたしが挑んだ曲一覧」に、まさにギャフン!でございます。
見事な難曲が並んでいるではありませんか!
やっぱり、おつむが、集中力が、能力が、違うんだろうなあ~……というのが正直なところ。
感服。
軽い文体で読みやすいけれど、だれにでもできる業ではございません。はい。
『鍵盤の天皇-井口基成とその血族-』
ハードカバーの立派な楽譜(春秋社版)の校訂者としてお馴染みの井口基成。ピアニストとしても教育者としても音楽界一の大人物だったのに、今や斎藤秀雄の陰に。その理由は?「血族」の語の重さよ!
著者: 中丸美繪
著者: 中丸美繪
出版社: 中央公論新社
価格: 3300円
発売日: 2022年05月23日


井口基成。1908年(明治41年)生まれ、1983年(昭和58年)没。
その人生を、ピアノ、音楽との関わりを中心としながら、家族との関係、私生活も含めてまとめ上げた労作です。全629ページ。
私、年上の先輩からも
「井口基成・井口秋子・井口愛子の3人が日本の音楽会を牛耳っていた」
という話を聞いたことがあります。
井口基成と結婚したのが、秋子。
基成の妹が、愛子。
井口家にピアノが来た経緯からすごいです。
指揮者として有名な渡邉暁雄の母シーリ(声楽家)が「故郷フィンランドからはるばる持参してきたもの」が、宣教師だった暁雄の父から、教会を通じてクリスチャンだった井口家へ来たとのこと。
男児たるもの、音楽などにうつつを抜かすべからず、という時代、
「うちは武士の出だ。お前はピアノを触るな」
と叱られた基成は、姉や妹がピアノを習うのを見て、密かに練習を重ねます。
妹の愛子は子供のころからめざましい才能を発揮。
いっぽう、基成がピアノを弾くことを父から許されたのは、基成16歳のとき。
彼は猛練習を始め、それからたった2年で東京音楽学校(今の藝大)に入ってしまうのです。
その後、フランスに留学。
ドイツ音楽一辺倒だった当時の日本音楽界に疑問を持って。
フランスの恩師・イーヴ・ナットのことばが身に沁みました。
「ピアノを弾くうえで、いちばん大事なことは指の先だ。指先の神経がちょうど人間の眼と同じように働いて鍵盤を捉えなければならない」「手首、腕、肩、すべての関節が楽になっているのはもちろんのこと、いつでもおおらかな気持ちで、無理なく弾けるようにならなければいけない」
ナットの言葉は抵抗なく基成に染み込んでいったとのことです。
NHKの音楽ディレクター増井敬二の井口評は以下のとおり。
「井口さんがそれまでのピアニストと違っていたのはタッチとリズム。明瞭度が格段に違う。それまでのピアニストは正確に弾けないし、音はモソモソしていて、コンチェルトは馴れ合いの芸術だった」
1942年には、今のNHK交響楽団、ローゼンストックの指揮によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」が、井口を「天皇」にしたと言います。
そして、35歳の若さで、音楽家として初の第二回帝国芸術院賞を受賞。
その後、船舶特別幹部候補生260人に対し音感教育に当たらされるも、何の専門教育も受けていない兵士への教育に抗議した結果、召集令状を受け取ることとなり、最低階級の二等兵として苦労する羽目に。
そのアップダウンぶりには驚かされます。
戦後、ピアニストとして、音楽学校の教師として既に活躍していた同僚・秋子と恋仲となり結婚。
賢婦の鏡、母、妻、教師、ピアニストの仕事を完璧にやり遂げる秋子との生活、
斎藤秀雄らとともに桐朋子供のための音楽教室、そして桐朋音大を創り上げていく様子が大変詳しく描かれます。
小澤征爾が立ち上げた「サイトウキネンオーケストラ」や音楽祭によって、斎藤秀雄の名前は広く知られています。
ところが、実際のレッスンでは、斎藤は暗くて、細かいところにこだわりすぎる神経質さで、あまり人気がなかったとも。
音楽評論家、吉田秀和も著名ですが、実は彼は桐朋立ち上げ時の事務方であり、問題を起こして追放されたりしたのでした。
当時、もっとも大車輪で活躍し、多くの人の信頼を勝ち得ていたのは、井口基成だったのです。
著者がこの本を書こうと思いたったのも、斎藤秀雄の伝記を執筆していたときに、
「井口基成の方が魅力的だった」
という声を数多く聞いたから、とのこと。
実際、この本で知る彼の活躍ぶりには目をみはります。
それがなぜ、今となっては斎藤秀雄、吉田秀和の名にすっかり水をあけられてしまったのか。
それは、女性スキャンダルだったのでした。
家柄もよく、完璧な妻であり、ピアノの弟子も多かった秋子の元を去り、
バーで働いていた若い女性と同居を始めた基成。
秋子との間に6人、後妻の妙子との間に3人の子をなしています。
ピアノの弟子には上流階級出身者、女性スキャンダルに厳しい家庭が多く、基成の元を去った者が多かった、と。
いやはや、このあたり、よ~くわかります。
怖いんですよ。潔癖な女性たちの集団力って。
「昭和という時代を駆け抜けた、スケールの大きい男の物語」でした。
この本、いろいろな読み方ができそうです。
『ジョルジュ・シフラ回想録;大砲と花』
著者: ジョルジュ・シフラ、八隅裕樹
出版社: 彩流社
価格: 3520円
発売日: 2021年11月05日


ジョルジュ・シフラ(1921~1994)は、ハンガリー生まれのピアニスト。
名前は何となく聞いたことはありましたが、その人物、人生については、この本で初めて知りました。
構成は以下のとおり。
前奏(プレリュード)第1章 貧困の筏第2章 サーカスリングにて第3章 行商人の予言第4章 ヘイル、シーザー!(カエサル、万歳!)第5章 嫉妬の死第6章 ピアノではなく、蒸気機関第7章 スターリンの連装砲(オルガン)第8章 ハンガリー狂詩曲第2番――失敗第9章 終わりなき夜第10章 全か、無か第11章 サン=フランブールへの巡礼の旅夜明け
彼の人生には戦争の影がずっとつきまとっています。
生まれたのは、ハンガリー・ブタペスト郊外の不衛生極まりない<仮設居住区>だったのですが、それも、第一次世界大戦のなせる業でした。フランス政府が「敵国出身の外国人居住者を国外へ追放」し「彼らの財産をとり上げ」るという対象者に、ハンガリー国籍の音楽家であった父が該当したのです。
極貧の生活の中、病気がちで、立つこともままならない、ひ弱な3歳児となった彼。
そんな中、皿洗いの仕事を得た姉が、アップライトピアノを賃借して家に運び込ませ、「持ち前の忍耐力と粘り強さで」練習に取り組み始めます。
ここからの展開に驚愕。
なんと幼いジョルジュは、「マットレスの上で横になりながら」、姉に合わせて「毛布の下で、すべての指の動きを丹念に真似し」、音階(スケール)も会得してしまいます。
病気が癒え、姉と交代でピアノに触れることができるようになると、父の手ほどきのもと、凄まじい勢いでピアノの演奏を上達させます。
楽譜なしで、母の歌からオペラやオペレッタの一節を知り、音楽の奥深さに気づき、小曲に自分で考えた序奏をつけたり、次々と装飾を施したりしるようになった。左手が右手と同じだけすばやく動くようになると、変奏にも取り組み始めた。(p.39)
と言います。
父から複雑な和声を習うと、それもすぐ身につけ、「自信をもってそれらを短いワルツや小曲――遊び半分で作った曲ーーの飾りつけに用いることができた」「あの素晴らしいシュトラウス一族やオッフェンバックなどの名曲の数々を、ひたすら即興的に弾いていった」という彼、このとき5歳。
その演奏のあまりの凄腕ぶりが評判を呼び、サーカスの公演に客演してお金を得るも、幼い体力が続かず。その後、やり手の行商人の手引きで「リスト音楽院」の校長の邸宅へ行った結果、「数奇な境遇のもとで音楽院への入学が認められ」るのです。
もう、ここまでで、驚くべき人生なのですが、実は本筋はここから。
第二次世界大戦、です。
メインとなる話は、残虐な上官による仕打ちや、不条理な軍隊生活。
ウクライナ戦線へと送られ、音楽とは隔絶されて送る悲惨な日々。
そんなある日、本営を訪れたドイツ軍の高官が「演奏」を求めたことから、ジョルジュがステージに引っ張り出され、2年のブランクにもかかわらず大喝采を浴びます。
そして、その高官から
「ベルリンの大本営に同行してくれれば、リヒャルト・シュトラウスにも紹介する」
と持ち掛けられ、24時間の猶予を与えられるのですが、なんと彼は、その足で「脱走兵」となって逃げだしたのでした。
理由は……妻がエジプト系であったこと。純アーリア人でない妻と息子は、ドイツでは生きられないと判断し、逃げるのが最善の道という判断を下したのでした。(第6章)
その後、捕虜となり、ドイツ軍の恩赦を受けてハンガリーへと戻り、新兵の訓練役となり、終戦後1年以上経った1946年9月になって軍務を解かれます。
家族との再会後、彼の活躍の場所となったのは、クラシック音楽とは無縁の労働者たちを聴き手とするバーやナイトクラブ、キャバレー。ジプシー楽団や、ジャズ楽団との共演。
現実に絶望し、亡命をはかったところを捉えられ、1950年から3年間は獄中生活を送ることに。
しかし、ジョルジュの演奏に熱狂した多くの聴衆からの手紙が、ハンガリー政府に届いたことから、コンサート・ピアニストとしての道が拓けていきます。
彼の辿ってきた道を考えれば、いわゆる「音楽批評家」の中には、彼の演奏を貶める人も多かったであろうことは想像に難くなく、彼らに対するジョルジュ側の辛口批評も読みごたえたっぷり。
また、楽譜を読み込みながら、模索を重ねる彼の真摯な姿も。
ノストラダムスのごとき透視力とピタゴラスのごとき理性とが上手く調和して初めて、潜在意識は様々な表現工程の整合性を取ることができる。私はその芸術表現の物差しを奪われていたために、自らの着想と演奏解釈に不安を感じていたのだ。(p.285)
最初の演奏会は「度を越した演奏技巧に頼りきりとなったことで、私の指先からはとめどなく退屈があふれ出た」ものの「最後にアンコールとして弾いた編曲と即興演奏が、見事にすべての埋め合わせをし」たと振り返ります。
冷戦時代のハンガリーで練習に励み、黙考し、次第に自信を取り戻していく彼。
「アルプスの湖のように平穏な鍵盤」を「神学や神智学を超えた主義信条を映し出す眩い鏡」に変貌させるのに必要なものは「忍耐力と信念だけ」であり、「自らの信条に実直であることが、他者の心を動かす巨大な力の源である」という結論に至ります。
さかのぼって第8章に記された、戦中の回想も、印象的でした。
ハンガリーで軍務にあたる中、急遽「紳士たちの特別な夜会」での演奏を求められ、10日間の準備での本番、周囲の勧めで演奏前に酒を飲んでしまった日についての記述です。
大失敗の記憶は、疼く傷のように心を苦しめ、その先何年も日ごと夜ごとに私を追い回した。実際、この苦い経験を忘れるためには、20年にもおよんで充実した演奏家生活を積み重ねていくことが必要だった。それ以外のどんな軟膏もこの苦痛を癒すことはできず、また、心のなかの深い傷を消すこともできなかった。(p.222)
天賦の才を持つピアニスト。
たった1回の演奏で、こういう思いをするのですね。
最終章は、亡命してフランスに居を構え、シフラ財団をつくって古い教会を買い取って修復し、フランツ・リスト音楽院を設立。若手演奏家の支援にあたるまで。
本書の原著は1977年のフランス語版。
著作権の問題などの障害を乗り越え、シフラ生誕100年を記念して出版されたとのことですが、今読むからこそ心に響くものが大きいと感じました。
おすすめです。
おすすめです。
『絶対! わかる 和声法100のコツ』
前作より版が大きくなり、1つのトピックが見開き2ページ以内で収まる形になっています。
うん、読みやすい。
著者の説明が2017年よりもわかりやすくなったのか、
読み手の私の方の基礎学力が、少しマシになったのか、
たぶん、その相互作用でしょう。
「理解してほしい」という著者の思いは、ビシビシ伝わります。
ただし、
あたり前のように「つまり、」と表現される箇所で「えっ?なぜ?」と頭がフリーズすることも。
あたり前のように「つまり、」と表現される箇所で「えっ?なぜ?」と頭がフリーズすることも。
私にとっての鬼門は、やはり「和音記号」(著者は「数字付低音」の記載法を薦める立場)。
そもそも、和音そのものの概念が未だあいまいなままの私にとって、その記載法の良しあしを論じられても、、、。
この本の定めるゴールは、高いのです。
100個並ぶコラムは全14章に分かれているのですが、第1章は「和声法はこんなことに役立つ」
で、冒頭、第1番目のコラムに書いてあるのが、こちら。
……「ピアノで音を探ってみないと、曲のイメージが湧かない」というのは、「楽譜から音楽を聴き取る」という努力を最初から放棄していたわけで、とてもよろしくない態度だったのです。
「と言われてもねぇ~」という方が多いのはよくわかる!しかしですね、慣れないうちは大変ですが、心を落ち着けて、慌てないで、ゆっくり楽譜を眺めるところから始めてみてください。少しずつ、少しずつ、想像力が働き始めますから。
そして、そのときに和声法で培った能力が役に立つのですよ。
わわわ、でもって、このページのまとめが
和声法を武器にした譜読みが 演奏には生かされる
多少わかるようになったとはいえ、「?」のままのページも多々。
何度も読まないと、ダメそうです。はい。(その気力があるのか、、、💦)
『和音の正体 ~和音の成り立ち、仕組み、進化の歴史~』
音楽愛好家で知識欲に溢れた方々をターゲットとした「和音」に特化した本(「おわりに」より)
著者: 舟橋三十子
出版社: ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス
価格: 1980円
発売日: 2022年02月24日


ええと、私、「知識欲」よりも「コンプレックス」に溢れ、途方に暮れている音楽愛好家であります(だって、下手くそなりにレッスン受けたり、解説読んだりするたびに、分からないことが続々と……)。
でもって、その分からなさの大部分を占めるのが、和音です。和声です。
本書の構成は以下の通り。
第1章 和音の基礎知識
第2章 和音の文法と性格
第3章 時台とともに変化する和音
第4章 作曲家による和音の好み
第5章 国ごとの和音の変化
第6章 さまざまな和音
第7章 音楽に広がりを与える和音
ざっと目を通しました。
今まで、あっちこっちの本やサイトをかじり読みして「その場の理解」をしては忘れ果てる……ということを繰り返してきたことが、まとまって参照できるだけでもありがたいです。
特に第4章。
「ナポリの和音」「ドリアの和音」「ピカルディの3度」「悪魔の音程」「トリスタン和音」……こういったものが、一発参照可能。
(たぶん、読んでは忘れ……を繰りかえすけれど、いつでも参照できる安心感!)
(たぶん、読んでは忘れ……を繰りかえすけれど、いつでも参照できる安心感!)
ただ、第6章を理解するには根気が必要です。
のちほど再チャレンジしようと思います。
のちほど再チャレンジしようと思います。
それ以外については、読みやすくて助かりました。
(身に着いたとは、とてもとても言えませんが。汗)
(身に着いたとは、とてもとても言えませんが。汗)
『演奏する喜び、考える喜び』
「音楽研究で学位を獲得するのは楽すぎる」ため、フランス文学で博士号を取得したコンサート・ピアニスト(兼音楽研究者)の対談記録。おつむの弱い読者(私)に理解できるのは半分ほど?
 本文は133ページほど。B5版で小さく、かつ薄いです。
本文は133ページほど。B5版で小さく、かつ薄いです。
著者: チャールズ・ローゼン、キャサリン・テマーソン、笠羽映子
出版社: みすず書房
発売日: 2022年05月11日
ISBN: 9784622090717

チャールズ・ローゼン(1927~2012)は、アメリカで活躍したピアニストにして音楽研究者。
そのピアノの師、モーリツ・ローゼンタール(1862~1946)は、リストの弟子で、1880年代にブラームスの目の前で卓越したピアノの腕を披露したことから、ブラームスと友人になったのだとか。
「リストやブラームスと直接の知り合いだった」人からピアノを習ったというピアニストが、つい最近まで活躍していた、という事実に、まず、びっくりしました。
そんな貴重な方の対談記録が本書、なのですが、
残念ながら、私自身に音楽学の知識が欠落していることもあって、いろいろなことが消化できないまま読了、、、という結果に。恥💦
章立ては以下のとおり。
- 音楽分析
- 音楽分析の成果
- 様式
- 音楽演奏
- 身体的喜び、知的喜び
- 演奏家の役割
備忘録として、何とか追いつけた箇所の抜き書きを残しておきます。
(実際には、具体的な作曲家、曲目についての分析例も収録。心得のある方はぜひお読みください。)
【音楽分析】
「分析は、それ自体で喜びをもたらすかもしれない」が、分析という観点を持たない優れた演奏家もいる(例えば、ピアニストのゼルキンは、練習によって、鍵盤上で演奏を練り上げていたのであって、楽曲分析によってはいないと考える)。
分析と演奏の関係の一般化はぼ不可能で、その人、その曲によって異なる。
演奏するということ自体がひとつの分析に等しく、著者にとっては分析と演奏は異なる行為。
【音楽分析の成果】
分析では、「各々の作曲家によって用いられている手法を強調し、「同時代の作曲家の音楽、あるいはその作曲家に先立ったり、続いた人たちの音楽とどう異なっているか」を示したい。
例えば、シューマンを「病的な気分に耽る大作曲家」と言うには、シューマンがこうした気分を音楽で喚起するために用いた「技法的手段」を拠り所が必要。
作曲家の仕事、その伝記、発言を曲の理解にどう生かすかは、その時代や曲による。
【様式】
音楽だけでなく、文学、絵画、建築などとの関わりの中で考えるべき。
ロマン主義に典型的な断片形式は、まず文学作品に現れ、1825年からは音楽にも現れた(展開部の中で始まるように思われ、最後に真の終止形を持たない作品)。
断絶と変換の時期に興味を惹かれる。1850年頃、ロマン主義の第一期が終わる時期に、ブラームスが古典派の大掛かりな形式を立て直す手段を発見し、ハイドンやモーツァルトの模倣を完全にモダンな音楽に組み入れた。
【音楽演奏】
作曲された当時の演奏を再現しようとする場合、疑わしい知識に頼るのは誤り。
楽譜を厳密に尊重することで間違ってしまうこともある。楽譜には製版者のミスがつきもの。
【身体的喜び、知的喜び】
演奏は身体的、筋肉の喜び(快楽)。指を鍵盤に触れさせることに強烈な喜びを感じることなくピアニストになることは不可能。
音は心の中で聞くものだが、ピアノという楽器において、これは非常に難しい。
音楽概念は、筋肉的なものと、知的なものという2つの喜びをもたらすが、これらは直接には聴覚には結びついていない。
【演奏家の役割】
演奏家はひとつの作品のもっとも興味深い長所を明らかにすべき。
諸々の作品を平板化し、伝統的な側面を強調しすぎて演奏を味気なくしてしまうのは誤りだと考える。
音楽のエレクトロニクス化は今後も進むだろうが、クラシック音楽の演奏に身体的な喜びを感じる音楽家たちが存在する限り、この音楽も存続するだろう。
『教養として学んでおきたいクラシック音楽』
東京藝大の学長にして、現役のヴァイオリニストである著者が、一般読者へ向けて発信したメッセージ。
著者: 澤和樹
著者: 澤和樹
出版社: マイナビ出版
価格: 957円
発売日: 2022年02月28日

冒頭は「ざっくりわかる17世紀~20世紀クラシック音楽年表」。
本書で言及した作曲家は太字になっていて、列挙すると、
・ヴィヴァルディ
・バッハ
・ハイドン
・モーツァルト
・ベートーヴェン
・シューベルト
・メンデルスゾーン
・シューマン
・プランク
・ブラームス
・ビゼー
・チャイコフスキー
・ドヴォルザーク
・ドビュッシー
・ラフマニノフ
・ラヴェル
・ストラヴィンスキー
・プロコフィエフ
なるほど。さすがヴァイオリニスト。
ショパン、リストは選外なんですね~。
本編は全7章。
・クラシック音楽の名曲カタログ(時代別)、
・著者ご自身の音楽家人生ふりかえり
・演奏会に行くこと、音源を聴くことのすすめ、
・クラシック音楽の今後
といった内容です。
印象に残ったのは、次のような点。
・日本の国家予算のうち、芸術振興にかけるのは0.1%あまり。
・それに対し、韓国は、国家予算の1.0パーセントを割いており、日本の9倍。
→韓国の若者たちが国際音楽コンクールで活躍している背景には、こういった事情も影響していそうですね。
・著者が愛奏している楽器は、グヮルネリ・デル・ジェスの「アークライト」と名付けられた名器(1732年製造。ハイドンの誕生年)。この楽器に出会った時大学院生だった著者は、地元の出身高校の先輩である支援者に相談したところ、「その方が何人かに声をかけ、共同で銀行からお金を借りて楽器を購入し、私に貸与してくださったのです」とのこと。
→演奏が優れてさえいれば、世に出られる……というものではなさそう。
周囲の人々を「こいつのためなら、人肌ぬいでやろう!」という気にさせてしまう人間的な魅力が必要なのでしょうね。
将来を見据え、藝大トップとして芸術を牽引していくべく、新たな試みに着手されているとのこと
(藝大の教員が地方に出向いてレッスン、才能を発掘して育てる「早期教育プレジェクト」、在学中の藝大学生のための「キャリア支援室」、芸術と人、サイエンスとの関係を解き明かすべく専門家の対談を公開する「アート・ミーツ・サイエンス(AMS)プロジェクト」等)、
なるほど、応援したくなりました。

冒頭は「ざっくりわかる17世紀~20世紀クラシック音楽年表」。
本書で言及した作曲家は太字になっていて、列挙すると、
・ヴィヴァルディ
・バッハ
・ハイドン
・モーツァルト
・ベートーヴェン
・シューベルト
・メンデルスゾーン
・シューマン
・プランク
・ブラームス
・ビゼー
・チャイコフスキー
・ドヴォルザーク
・ドビュッシー
・ラフマニノフ
・ラヴェル
・ストラヴィンスキー
・プロコフィエフ
なるほど。さすがヴァイオリニスト。
ショパン、リストは選外なんですね~。
本編は全7章。
・クラシック音楽の名曲カタログ(時代別)、
・著者ご自身の音楽家人生ふりかえり
・演奏会に行くこと、音源を聴くことのすすめ、
・クラシック音楽の今後
といった内容です。
印象に残ったのは、次のような点。
・日本の国家予算のうち、芸術振興にかけるのは0.1%あまり。
・それに対し、韓国は、国家予算の1.0パーセントを割いており、日本の9倍。
→韓国の若者たちが国際音楽コンクールで活躍している背景には、こういった事情も影響していそうですね。
・著者が愛奏している楽器は、グヮルネリ・デル・ジェスの「アークライト」と名付けられた名器(1732年製造。ハイドンの誕生年)。この楽器に出会った時大学院生だった著者は、地元の出身高校の先輩である支援者に相談したところ、「その方が何人かに声をかけ、共同で銀行からお金を借りて楽器を購入し、私に貸与してくださったのです」とのこと。
→演奏が優れてさえいれば、世に出られる……というものではなさそう。
周囲の人々を「こいつのためなら、人肌ぬいでやろう!」という気にさせてしまう人間的な魅力が必要なのでしょうね。
将来を見据え、藝大トップとして芸術を牽引していくべく、新たな試みに着手されているとのこと
(藝大の教員が地方に出向いてレッスン、才能を発掘して育てる「早期教育プレジェクト」、在学中の藝大学生のための「キャリア支援室」、芸術と人、サイエンスとの関係を解き明かすべく専門家の対談を公開する「アート・ミーツ・サイエンス(AMS)プロジェクト」等)、
なるほど、応援したくなりました。
『歌舞伎を救ったアメリカ人』
米軍による日本占領期にマッカーサーとともに来日し、歌舞伎上演のために奔走した米国人が、NYのジュリアード音楽院でピアノを学んだ音楽家であったという事実にびっくり……ただ、音楽関係について掘り下げた本ではありません。
実はこの本、「ジュリアード音楽院」がどれほど権威のある教育機関であるか、ということを説明していたYouTuberの方が引き合いに出されたことで、知りました。
著者: 岡本嗣郎
出版社: 集英社
価格: 208円
発売日: 2001年12月14日
ISBN: 9784087473964
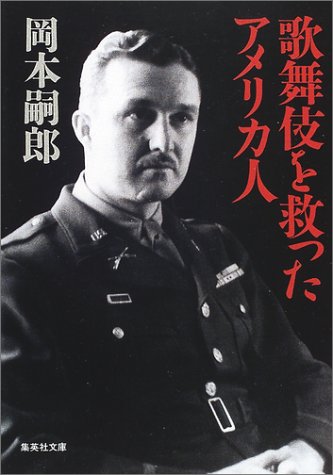
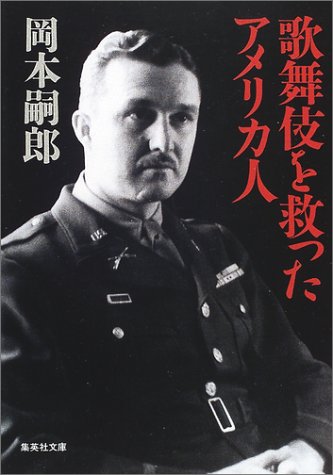
実はこの本、「ジュリアード音楽院」がどれほど権威のある教育機関であるか、ということを説明していたYouTuberの方が引き合いに出されたことで、知りました。
私、この3月に京都の南座まで赴いて歌舞伎を見てきたところですし、若かりし頃は歌舞伎座の安い3階席で歌舞伎鑑賞したことも多々。「これは読まねば!」と思った次第です。
歌舞伎を救ったアメリカ人、その名はフォービアン・パワーズ。
1917年(大正6年)生まれで、1945年の来日時、28歳だったアメリカ陸軍少佐です。
筆者は1997年(平成9年)の5月と12月、ニューヨークにパワーズ本人を訪ね、インタビューしたそうです。(p.12)
また、1960年(昭和35年)10月、43歳のときにニューヨークで受けた、米国政府機関のインタビュー記録「フォービアン・パワーズ回想録」(コロンビア大学オーラルヒストリー研究所所蔵)を取り寄せて翻訳したとのこと。(p.52-53)
ただ、パワーズ自身の記憶違い(これは筆者も度々指摘しています)、自身の功績を誇張して時に事実を捻じ曲げる傾向もあったようで、本書の出版後に異論も多々出ているようです(Wikiによれば、そもそも「マッカーサーの副官という触れ込みも嘘で、本当はボナー・フェラーズ准将の部下(通訳)」なのだとか)。このあたりは、私としては
「そういったことは、ありがちだよなあ」
といった程度の感想です、はい。
CIE(民間情報教育局)と、総司令部(GHQ)の関係、
「鳳舞(ほうぶ・フォーブ)ちゃん」と呼ばれて、歌舞伎役者とやりとりした手紙、メモの文体、内容など、興味深く読みました。
一部の著名な歌舞伎役者と大変に親しく付き合い、占領期に歌舞伎役者たちを支援したことは事実のようです。
アメリカン・インディアンの血もひいているという出自が、インドネシアの音楽や、日本の歌舞伎への興味につながったのかなあと思います。
確かに1940年、50年代に、西欧至上主義とは一線を画す文化観を持っていたというだけでも、稀有な存在と言っていいでしょう。
また、フォーブスという人間ドラマだけでなく、歴史を捉え直す面白さも味わえました。
印象的だったのは、昭和天皇とマッカーサーとの面会についてです。
昭和天皇(当時44歳)がマッカーサー(当時65歳)を訪ねた際、アメリカ側は「天皇が命乞いに来た」と考えたのに対し、天皇は
「戦争は私の名のもとに起こったことだから、すべては私の責任である。巣鴨の収容所にいる戦争犯罪者を解放して、私を身代わりにしてほしい。」
といった内容のことを訴え、マッカーサーは天皇に感服してしまった、という話。
私も新聞か何かで読んで、感銘を受けた記憶があります。
ところが、これ、マッカーサーの回想録に記載されている内容で、真実ではなさそうだというのです。
筆者は、マッカーサー回想録は1964年出版で、会見から19年も後のことであり、内容は事実誤認、誇張、曲解に満ちていると指摘します。
天皇の発言については
・天皇が戦争の全責任を負うと明言したとする立場
・それを疑問視する立場
の二種の立場があり、筆者自身で日本に残るさまざまな資料にあたった結果、天皇が戦争責任を「明言」したという記述はない、と書きます。
そして、この会見を機に天皇の戦争責任追及は終息に向かい、マッカーサーの天皇制擁護と占領における天皇の政治的利用が前面に出てくることを指摘し、「天皇は日本の最上の紳士」であることを強調するのが、マッカーサーの狙いだったと結論づけるのです。
天皇の処遇は米国政府の高度な政治的判断で決まった。アメリカの日本占領を円滑ならしめるために、天皇は戦争責任を免除された。天皇の免責は、あくまでアメリカ政府の政治的判断だった。(p.238)
なるほど。
有力者一人と一人の会見で、大きく歴史が変わった!
とする見方は、多々見受けられますけれど、結局は、その背後には実は組織の大きな力が働いていた、というのが多いのかもしれません。
音楽院という言葉をきっかけに読み始めた本ですが、音楽関係の記述はほとんどなく、人間の性(さが)や、歴史の作られ方といったものについて考えさせられました。
『ラドゥ・ルプーは語らない』
- 『ラドゥ・ルプーは語らない――沈黙のピアニストをたどる20の素描(デッサン)――』
- 著者: 板垣千佳子[編]
- 出版社: アルテスパブリッシング
- 価格: 2640円
- 発売日: 2021年11月19日
2022年4月17日にスイス、ローザンヌのご自宅で天に召されたピアニスト、ラドゥ・ルプー(1945年11月30日、ルーマニア生まれ、76歳)。 - 2019年6月にピアニスト引退後、3年を経ずして帰らぬ人となってしまいました。
- この本の著者(編者)は、1991年から2013年まで計」7回の日本ツアーに同行した担当マネージャーです。
- 録音も少なく、TV出演もインタビューもほとんど受けなかったルプー。
- その引退公演の翌日、著者はルプーに
- 「あなたに関する本を日本で出版したいと思っています。お許しいただけますか?」
- と尋ね、
- 「チカコ、僕自身はもちろん語らないけれど、君がそうしたいなら、すべてまかせるよ。実り多いことを祈っている」
- との回答を得たのだそうです。(「はじめに」より)
目次
Part1 20のインタビューと寄稿によるラドゥ・ルプーの物語
- 寄稿 サー・アンドラーシュ・シフ(ピアニスト)
- インタビュー ミッシャ・マイスキー(チェロ奏者)
- 寄稿 ボリス・ペトルシャンスキー(ピアニスト)
- 寄稿 アンヌ・ケフェレック(ピアニスト)
- インタビュー チョン・キョンファ(ヴァイオリン奏者)
- インタビュー ディディエ・コッティニー(オーケストラ事務局長)
- インタビュー ジェシカ・ナスミス&ロビン・ラフ(マネージャー、BBCディレクター)
- インタビュー ガスリー・リューク(ピアニスト)
- 寄稿 ジェニー・フォーゲル(マネージャー)
- インタビュー ヘレン・ターナー(マネージャー)
- インタビュー ダニエル・バレンボイム(指揮者、ピアニスト)
- インタビュー フランツ・ウェルザー=メスト(指揮者)
- 寄稿 フィリップ・カサール(ピアニスト)
- インタビュー ジャン=エフラム・パウゼ(ピアニスト)
- インタビュー ミシェル・ブランジェス(調律師)
- ネルソン&ルスダン・ゲルナー(ピアニスト)
- インタビュー ユリアンナ・アヴデーエワ(ピアニスト)
- インタビュー チョ・ソンジン(ピアニスト)
- 寄稿 スティーヴン・イッサ―リス(チェロ奏者)
- エリザベス・ウィルソン(作家)
Part2 ルプーのほうへ 青澤隆明

まさに、ルプー本人の弁、筆は皆無。題名そのままです。
そうそうたる20名の弁や記述から、商業主義やポピュリズムとは距離をとり、真摯に芸術を追い求めたルプーの人柄が浮かび上がります。
20番目に名前が挙がっている「エリザベス・ウィルソン(作家)」とは、ルプーの最初の結婚相手。
彼女の名前を挙げたのが、現・デリア夫人だといいます。
ルプーがリーズ国際コンクールを受け、優勝後にイギリスに居を構えたのも、モスクワ留学中に、イギリス国籍の彼女と出会ったからこそ、だったのでしょう。若い頃のエピソードが満載で、最も読ませる内容になっています。
1970年、ミッシャ・マイスキーが、弓を買うためにドルを入手したことで「投機」容疑を受け、モスクワで逮捕、投獄、工場での強制労働の憂き目にあったが、見て見ぬふりをする教授陣が多かった、とか
1969年のリーズ国際でルプーが優勝できたのは、ロシアからの参加者をファイナルに残すため、3人のはずのファイナリストを審査員のゴリ押しで5人に増やしたからこそだ、とか
その審査員たちの議論をめぐるゴシップはたちまち参加者の間に広まった、とか。
有名なロシア人教師、ネイガウスの直弟子と形容されるが、実際にはほとんどレッスンは受けないままネイガウスは亡くなってしまい、その息子のスタシック・ネイガウスと、音楽的にも個人的にも親しい間柄になったとのこと。
ソ連在住だったスタシックは、国外に演奏旅行に出るにも政府との折衝で大きなストレスがかかり、1976年、フランス、トゥレーヌで開催されたリヒテルの音楽祭での演奏に傷がついたことで打ちのめされ、酒におぼれたが、そのことをリヒテルが自伝の中でルプーのせいだとする大嘘を書いた、とか。
この世代の方々って、戦争や政治の影響を多大に受けつつ生きて来たのだなあ、、ということを改めて思い知らされた読後感でした。
また、
ソンジン君が、ルプーのCDジャケットの写真が「ブラームスに似ている」ことで手に取り、その音楽にのめりこんだ、というエピソード、
ルプー自身が、もし彼が今のソンジン君のように自由にいろいろな曲や楽譜に触れることができていたら、人生が変わっていただろうと述べた、とのエピソードが心に残りました。
(ドイツ音楽限定で録音しているように見えるのは、そういう時代背景があったのですね)
『フォルテピアノ 19世紀ウィーンの製作家と音楽家たち』
著者: 筒井はる香
出版社: アルテスパブリッシング
価格: 2420円
発売日: 2020年03月24日

本文は、あとがき含めて全164ページ。コンパクトにまとまっていて、読みやすいです。
巻末には、主要人名索引と「1791年から1833年までのウィーンにおけるピアノ製作家のリスト」391人分を掲載。タイトル通りの内容が腑に落ちます。

本文は、あとがき含めて全164ページ。コンパクトにまとまっていて、読みやすいです。
巻末には、主要人名索引と「1791年から1833年までのウィーンにおけるピアノ製作家のリスト」391人分を掲載。タイトル通りの内容が腑に落ちます。
目次を簡略化して示すと、以下の通り。
第1章 ピアノ製作の始まり(欧州諸都市の動向、鍵盤楽器の種類)
第2章 ウィーンのピアノ製作家たち(出身や活動地域など)
第3章 シュトライヒャーの社史(18世紀後半~19世紀前半)
第4章 ベートーヴェンの時代におけるピアノの技術革新
第5章 シュトライヒャーの顧客たち
第6章 楽器の特徴からベートーヴェンのピアノ・ソナタを読む
終章 ウィーンのフォルテピアノの「今」
「まえがき」の次の言葉が、本書の意図をはっきり示しています。
本書でめざしているのは、ピアノのための主要なレパートリーの大部分が作曲された19世紀前半のウィーン式ピアノ、およびその製作家に焦点をあてて、音楽史を描くことである。
18世紀以降、ピアノは、イギリス式ピアノとウィーン式ピアノの二つの様式に分かれて発展した。前者は技術革新を重ね、やがてモダン・ピアノへと受け継がれていくが、後者は、19世紀前半に興隆期を迎えた後、徐々に衰退の道をたどり、長い歴史の中で淘汰されてしまった。
現在、さまざまなYouTuber(と言っていいのかどうかわかりませんが)の方々が、動画を通じて「ピアノの弾き方」「ピアノという楽器の構造」などを解説しています。
本書冒頭の「ピアノの基本的な構造(1800年代のウィーン式ピアノの場合)」という写真入り解説を見ると、ウィーン式ピアノの「打鍵機構」(跳ね返り式)は、現在の方式(突き上げ式)に比べると、なるほど単純。
衰退しちゃったわけだよね……と思ったのですが、
よく言われているように、軽いタッチ、明るく明瞭な音色、という魅力も。
その背景には「ウィーン式ピアノには独自の製作様式とそれを支える、音や演奏に対する美意識がある」(p.152)と考えられるわけで、終章では、1828年創業後、現在まで続くベーゼンドルファー社を
「現代においてウィーンの伝統を受け継ぐ唯一の会社」
と定義し、考察対象としていて、この箇所もおもしろかったです。
- ベーゼンドルファー社の製作するピアノは、現在ではすべて突き上げ式だが、実は楽器の特色はアクションの種類だけで決まるわけではない。響板の素材や厚み、設計(高音部側の響板とピアノ本体のケースとの間に隙間を設ける)、本体ケースの素材(響板と同一素材を使う)などにより、現在でもウィーンの伝統的な響きが楽器に現れている場合がある。
- もともと軽さや明瞭さを追求したウィーン式悪性の場合、ハンマーの柄が鍵に直接固定されていることから、音量を増大させるためにハンマー・ヘッドの重量を増やすと、指にかかる負担も大きくなり、演奏に支障が生じる。音量増大は構造的に困難。
顧客からの要望を受けて、いわゆる受注生産で楽器を製作し、職人技を重んじたウィーン。
産業革命を経て、鋼鉄なども使い、工場での生産を可能にしていったイギリス。
世の流れとしては、
世の流れとしては、
市民社会の成熟とともに音楽ホールも大きくなり、大音量、頑丈さが求められるようになっていったわけで、どちらに軍配が上がるかは明白です。
最終的に他を圧倒したのがアメリカのスタインウェイであったことは、周知のこと。
いろいろ面白く読みました。
『音楽する脳 天才たちの創造性と超絶技巧の科学』
著者: 大黒達也
出版社: 朝日新聞出版
価格: 891円
発売日: 2022年02月10日

初めに言い訳。熟読はしていません。表面を撫でただけ、な感じ。
筆者は1986年生まれの研究者。
東大ドクター課程修了、オックスフォード大、ケンブリッジ大勤務などを経て、
現在は灯台国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構に所属。
なるほど、
「です・ます」体で書かれてはいますが、内容はばっちり学術的です。
全5章仕立てで、
各章の末尾4~8ページが「注」と「参考文献リスト」に充てられています。
第1章 音楽と数学の不思議な関係
第2章 宇宙の音楽、脳の音楽
第3章 創造的な音楽はいかにして作られるか
第4章 演奏家たちの超絶技巧の秘密
第5章 音楽を聴くと頭がよくなる?
第1章はピタゴラス音律とか、平均律の話など、今までに断片的に耳にした話をがっつりまとめていただいた感じです。音楽、科学(特に数学)、進化、全部つながってますよ!という話。
第2章、第3章は関連していて、「統計学習」がキーワード。人間の慣れと、新奇なものに反応する脳との相互作用で音楽が生まれる、といった話。
おもしろかったのが、
「脳に障害がありながらも卓越した曲を生む作曲家」という節。
ラヴェル(1875-1937)は、緩徐進行性失語症を患っていたのですが、「ボレロ」(1928年)、「左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調」(1930年)、「ピアノ協奏曲 ト長調」(1931年)などは、脳障害の症状発症後の作曲なのだそうです。1934年には文字の判読もできなくなり、無感情で表情の変化も消えたのに、彼の頭の中では素晴らしい曲の構想が練られていた(でも、楽譜に書き記すことは不可能)のだとか。
言語機能が侵されても音楽が創造できたのだから、音楽には言語を超えた何かがある!という指摘に、はっとさせられました。
他にも、
ガーシュインが、音楽の処理に重要とされる右側頭葉に膠芽腫という脳腫瘍を患っていたこと、
ロベルト・シューマンの精神障害などにも言及しています。
第4章、第5章は、音楽の演奏が、高次な脳の活動を引き起こすことを、いろいろなデータを使って紹介しています。
最後の節「音楽の脳疾患への効果」の内容にも興味をひかれました。
音楽を臨床に生かすという発想は、今、どんどん広がっているようです。
脳卒中、失語症、認知症、自閉スペクトラム症の治療、リハビリに、明らかな効果が見られるのだそうです。
時間ができたら、読み飛ばしたところもじっくり読んでみようと思います。

初めに言い訳。熟読はしていません。表面を撫でただけ、な感じ。
筆者は1986年生まれの研究者。
東大ドクター課程修了、オックスフォード大、ケンブリッジ大勤務などを経て、
現在は灯台国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構に所属。
なるほど、
「です・ます」体で書かれてはいますが、内容はばっちり学術的です。
全5章仕立てで、
各章の末尾4~8ページが「注」と「参考文献リスト」に充てられています。
第1章 音楽と数学の不思議な関係
第2章 宇宙の音楽、脳の音楽
第3章 創造的な音楽はいかにして作られるか
第4章 演奏家たちの超絶技巧の秘密
第5章 音楽を聴くと頭がよくなる?
第1章はピタゴラス音律とか、平均律の話など、今までに断片的に耳にした話をがっつりまとめていただいた感じです。音楽、科学(特に数学)、進化、全部つながってますよ!という話。
第2章、第3章は関連していて、「統計学習」がキーワード。人間の慣れと、新奇なものに反応する脳との相互作用で音楽が生まれる、といった話。
おもしろかったのが、
「脳に障害がありながらも卓越した曲を生む作曲家」という節。
ラヴェル(1875-1937)は、緩徐進行性失語症を患っていたのですが、「ボレロ」(1928年)、「左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調」(1930年)、「ピアノ協奏曲 ト長調」(1931年)などは、脳障害の症状発症後の作曲なのだそうです。1934年には文字の判読もできなくなり、無感情で表情の変化も消えたのに、彼の頭の中では素晴らしい曲の構想が練られていた(でも、楽譜に書き記すことは不可能)のだとか。
言語機能が侵されても音楽が創造できたのだから、音楽には言語を超えた何かがある!という指摘に、はっとさせられました。
他にも、
ガーシュインが、音楽の処理に重要とされる右側頭葉に膠芽腫という脳腫瘍を患っていたこと、
ロベルト・シューマンの精神障害などにも言及しています。
第4章、第5章は、音楽の演奏が、高次な脳の活動を引き起こすことを、いろいろなデータを使って紹介しています。
最後の節「音楽の脳疾患への効果」の内容にも興味をひかれました。
音楽を臨床に生かすという発想は、今、どんどん広がっているようです。
脳卒中、失語症、認知症、自閉スペクトラム症の治療、リハビリに、明らかな効果が見られるのだそうです。
時間ができたら、読み飛ばしたところもじっくり読んでみようと思います。
『ゲーテとベート―ヴェン』
ベートーヴェン初期ピアノ・ソナタの公開セミナーで、まさに標記のことが話題に出たので、興味を持って読んでみました。
著者: 青木やよひ
出版社: 平凡社
頁数: 251P
発売日: 2004年11月01日

2018年に実際にワイマールを訪ね、ゲーテの家、ゲーテ博物館も見てきた私。
(→その記録)
(フランクフルト出身の)ゲーテがワイマル公国に招かれたのは、彼の著書に感銘を受けていたカール・アウグスト公が、18歳でその君主となったからだった。だが、おそらくそれは、摂政役をつとめていた公母アンナ・アマ―リアのはからいでもあった。彼女は大火で荒廃したワイマル宮廷を立て直そうとして、ドイツ各地の有能な人材を探していたからだ。(p.72)
なるほど。簡潔にして要を得た説明。
ボン出身のベートーヴェンが、ウィーンで活躍したことは、周知のとおりです。
本書では、ゲーテとベートーヴェンが実際に会ったボヘミアの湯治場(夏の保養地)であるカールスバート、テプリッツに残る資料、二人の身近な人々の手紙などをもとに、二人の関係を丹念に洗い直します。
そして、ロマン・ロランが同名の書『ゲーテとベートーヴェン』で著した
「二人はボヘミアで決裂し、その関係が修復されることはなかった」
という見方を覆すのです。
ゲーテ、1749年生まれ、
ベートーヴェン、1770年生まれ。
ボヘミアで出会った1812年には、61歳と42歳。
この時代、手紙のやりとりが頻繁になされ、それが現代にまで引き継がれているのですね。
中でも、女性たちの姿が、筆者の手で生き生きと描き出されています。
印象深かったのが、
「両巨匠をつなぐベッティーナ(p.99)」
と見出しにもなっている、ベッティーナ。
彼女、
ゲーテが若き20代の頃に恋愛関係にあった女性マクセ(紆余曲折あり、ゲーテとマクセの関係が『若きウェルテルの悩み』に結実した、とのこと)の娘で、母の死後、21歳のとき(1806年)、ゲーテと母がやりとりした手紙の束を、祖母の家で発見。
18年も前の新書本ですが、今読んでも、古びていないと感じます。

2018年に実際にワイマールを訪ね、ゲーテの家、ゲーテ博物館も見てきた私。
(→その記録)
(フランクフルト出身の)ゲーテがワイマル公国に招かれたのは、彼の著書に感銘を受けていたカール・アウグスト公が、18歳でその君主となったからだった。だが、おそらくそれは、摂政役をつとめていた公母アンナ・アマ―リアのはからいでもあった。彼女は大火で荒廃したワイマル宮廷を立て直そうとして、ドイツ各地の有能な人材を探していたからだ。(p.72)
なるほど。簡潔にして要を得た説明。
ボン出身のベートーヴェンが、ウィーンで活躍したことは、周知のとおりです。
本書では、ゲーテとベートーヴェンが実際に会ったボヘミアの湯治場(夏の保養地)であるカールスバート、テプリッツに残る資料、二人の身近な人々の手紙などをもとに、二人の関係を丹念に洗い直します。
そして、ロマン・ロランが同名の書『ゲーテとベートーヴェン』で著した
「二人はボヘミアで決裂し、その関係が修復されることはなかった」
という見方を覆すのです。
ゲーテ、1749年生まれ、
ベートーヴェン、1770年生まれ。
ボヘミアで出会った1812年には、61歳と42歳。
この時代、手紙のやりとりが頻繁になされ、それが現代にまで引き継がれているのですね。
中でも、女性たちの姿が、筆者の手で生き生きと描き出されています。
- 避暑に訪れた先で、通りを隔てて向かいの宿に仲良しの女性が宿泊していたら、それは女性同士、近況報告やゴシップ話に花を咲かすだろう。
- 進歩的な考えを持った女性が、これと思い定めた目標を抱いたら、その行動力は目覚ましい。
- しかし、このような進歩的な女性は、往々にして相手に詫びる如才なさに欠けている。
印象深かったのが、
「両巨匠をつなぐベッティーナ(p.99)」
と見出しにもなっている、ベッティーナ。
彼女、
ゲーテが若き20代の頃に恋愛関係にあった女性マクセ(紆余曲折あり、ゲーテとマクセの関係が『若きウェルテルの悩み』に結実した、とのこと)の娘で、母の死後、21歳のとき(1806年)、ゲーテと母がやりとりした手紙の束を、祖母の家で発見。
「それまで、国民的大詩人でありワイマル公国の宰相としてのゲーテしか知らなかった彼女にとって、それは青天の霹靂」
だったベッティーナは、84通の手紙を写しとり、ゲーテの母を訪ねます(二人ともフランクフルト在住)。
そして、ゲーテの母とすぐさま意気投合し、彼女の語るゲーテのエピソードを聞き取るのです。
おそるべし、ベッティーナの行動力。
その結果、ゲーテが後日、自伝『詩と真実』を執筆した際、誕生から幼年時代のことを知るベッティーナに頼ることになるのです(ゲーテの母は1808年に他界)。
そして、1807年、ベッティーナは「ワイマルで、実際にゲーテに会いたい!」と思いつめます。
しかし、当時、欧州はナポレオン戦争の真っただ中。
フランクフルトからベルリンに赴く予定のあった妹夫婦から
「もし同道するなら、帰路をワイマル経由にしてもよい」
との言葉を引き出し、
「もちろん、ベッティーナは勇躍出発した。しかしそれば、劇画もどきの冒険旅行だった。女性二人は男装して、闘っている敵味方の軍隊の間を通りぬけ、ベッティーナは旅行中ずっと馬車の御者台の上で過ごした」
という旅程をこなしたのでした。
ゲーテが、かつての恋人の面影のある若い女性の訪問を喜び、親しく付き合ったことは言うもでもありません。
また、1810年に初めてウィーンを訪ねたベッティーナは、ビルケンシュトック伯爵邸(異母兄フランツの妻アントーニアは、ビルケンシュトック家の娘)で、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの演奏を聴き衝撃を受けます。
そして、ベートーヴェンに会いたいと言い張り、実際に面会。
この時期、ベートーヴェンは「仕事の上で彼はまさに"ゲーテづいて"」いて、『ファウスト』『エグモント』などのゲーテの作に取り組んでいたのでした。
急に目の前に現れた「黒い捲毛と情熱的な瞳をした」ベッティーナは、ベートーヴェンにとってゲーテの詩による「君よ知るやかの国」(前年に作曲したばかり)に出てくる「ミニョンそっくりの女性」に見え、この曲をピアノで弾き、歌ってみせたベートーヴェンだったのでした。
そして、ゲーテの母とすぐさま意気投合し、彼女の語るゲーテのエピソードを聞き取るのです。
おそるべし、ベッティーナの行動力。
その結果、ゲーテが後日、自伝『詩と真実』を執筆した際、誕生から幼年時代のことを知るベッティーナに頼ることになるのです(ゲーテの母は1808年に他界)。
そして、1807年、ベッティーナは「ワイマルで、実際にゲーテに会いたい!」と思いつめます。
しかし、当時、欧州はナポレオン戦争の真っただ中。
フランクフルトからベルリンに赴く予定のあった妹夫婦から
「もし同道するなら、帰路をワイマル経由にしてもよい」
との言葉を引き出し、
「もちろん、ベッティーナは勇躍出発した。しかしそれば、劇画もどきの冒険旅行だった。女性二人は男装して、闘っている敵味方の軍隊の間を通りぬけ、ベッティーナは旅行中ずっと馬車の御者台の上で過ごした」
という旅程をこなしたのでした。
ゲーテが、かつての恋人の面影のある若い女性の訪問を喜び、親しく付き合ったことは言うもでもありません。
また、1810年に初めてウィーンを訪ねたベッティーナは、ビルケンシュトック伯爵邸(異母兄フランツの妻アントーニアは、ビルケンシュトック家の娘)で、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの演奏を聴き衝撃を受けます。
そして、ベートーヴェンに会いたいと言い張り、実際に面会。
この時期、ベートーヴェンは「仕事の上で彼はまさに"ゲーテづいて"」いて、『ファウスト』『エグモント』などのゲーテの作に取り組んでいたのでした。
急に目の前に現れた「黒い捲毛と情熱的な瞳をした」ベッティーナは、ベートーヴェンにとってゲーテの詩による「君よ知るやかの国」(前年に作曲したばかり)に出てくる「ミニョンそっくりの女性」に見え、この曲をピアノで弾き、歌ってみせたベートーヴェンだったのでした。
この時期、耳の不調は深刻だったのに。
そして、ベッティーナは「ベートーヴェンの天才の火花に感電」。
以降、それまではベートーヴェンの音楽に懐疑的だったゲーテに対して、
ベートーヴェンの素晴らしさを、必死で説くようになったベッティーナ。
ただ、それも、ゲーテの妻・クリスティーナと1811年に決裂するまでの4年間のことになります。
ゲーテとベートーヴェンが実際に会ったのは1812年。
このとき、ベッティーナも、また、会話がうまくできないベートーヴェン側に立ってくれる人もいない、との状況に。
このとき、
ゲーテ側も粗野なベートーヴェンに幻滅。以来、二人は決裂。
……という定説があったのですが、筆者は、さまざまな人々の手紙や記録をもとに、決してそうではないことを、ゲーテがベートーヴェンの曲を賞賛していること、彼の手書きの楽譜を所持していることを自慢していたことなどを明らかにしていきます。
次の一節も、印象に残りました。
ゲーテも、ベートーヴェンも、生き生きとした生身の人間として、行間から立ち上がってきました。そして、ベッティーナは「ベートーヴェンの天才の火花に感電」。
以降、それまではベートーヴェンの音楽に懐疑的だったゲーテに対して、
ベートーヴェンの素晴らしさを、必死で説くようになったベッティーナ。
ただ、それも、ゲーテの妻・クリスティーナと1811年に決裂するまでの4年間のことになります。
ゲーテとベートーヴェンが実際に会ったのは1812年。
このとき、ベッティーナも、また、会話がうまくできないベートーヴェン側に立ってくれる人もいない、との状況に。
このとき、
- 偉そうに振る舞う王族に、対抗心を燃やして道を譲らないベートーヴェン
- すぐさま道を譲り、恭しく礼をするゲーテ
ゲーテ側も粗野なベートーヴェンに幻滅。以来、二人は決裂。
……という定説があったのですが、筆者は、さまざまな人々の手紙や記録をもとに、決してそうではないことを、ゲーテがベートーヴェンの曲を賞賛していること、彼の手書きの楽譜を所持していることを自慢していたことなどを明らかにしていきます。
次の一節も、印象に残りました。
ゲーテは24歳で『ヴェルテル』に青春の情念を結晶させたが、それと双璧をなすものが、ベートーヴェンの場合、25歳で作曲されたピアノ・ソナタ『悲愴(パテティーク)』だといってよいだろう。
「グランド・ソナタ・パテティーク」という出版時(1799年)の標題は彼自身がつけたものである。ほこにはまさに青春のパトスが、叩きつけるように表現されている。
この作品は、発表と同時に若い世代から熱狂的に迎えられたが、反面、ウィーンのアカデミックな音楽教師たちは、学生にこの破天荒な作品をまねるのはもちろん、楽譜を見ることさえ禁じたという。これも『ヴェルテル』の場合に似ている。また、ウィーンに来た当初、"悪魔の指を持つ男"とよばれ、ピアニストとしての名声が先行していたベートーヴェンにとって、これは作曲家としてと彼を印象づける衝撃的デビューだった、といってよいだろう。(p.90)
18年も前の新書本ですが、今読んでも、古びていないと感じます。

